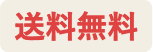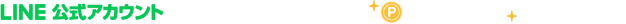この記事では、いただいた出産祝いへのお返し(内祝い)の相場金額や、大人として知っておきたい贈答マナーについて解説します。
赤ちゃんが生まれて出産祝いをもらったら、次に気になるのはお返しですよね。
「みんないくらぐらいのお返しをしてるものなの?」
と、相場が気になる新米ママ・パパは少なくありません。
出産祝いのお返し金額には、ふさわしい相場があります。
相場からあまりにも外れた金額のお返しをするのは失礼に当たるため、この際しっかり確認しておきましょう。
▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
目次
- 1 大前提:いただいた出産祝いに「お返しする」という表現は避けよう
- 2 出産祝いのお返し金額、相場は「半額~1/3」の範囲
- 3 【兄弟姉妹へ】出産祝いのお返し金額は年齢も考慮
- 4 【両親へ】出産祝いのお返し金額は相場より少ないことも
- 5 【親戚へ】出産祝いのお返し金額は年齢・付き合いの深さで判断
- 6 【友達へ】出産祝いのお返しは「前にもらった金額」も参考に
- 7 【上司・同僚へ】出産祝いのお返し金額は周囲に合わせることが大事
- 8 お返し金額はいくら? 迷う事例①「もらった出産祝いが連名だった」
- 9 お返し金額はいくら? 迷う事例②「出産祝いの値段が不明」
- 10 お返し金額はいくら? 迷う事例③「出産祝いが現金+品物だった」
- 11 お返し予算が決まった! 出産内祝いの贈り方マナーを確認
- 12 出産祝いのお返し金額を軽減! リーズナブルな選び方
- 13 出産祝いのお返しに! 金額別の人気ギフト紹介【専門店おすすめ】
- 14 人生の節目の出産内祝い、失礼のないお返しを
大前提:いただいた出産祝いに「お返しする」という表現は避けよう

出産祝いをもらったときは、「内祝い」という名目でお返しを贈ります。
内祝いとは日本古来の贈答習慣で、本来は「内(内輪、身内)のお祝い」を意味します。
「身内におめでたいことがあったときに、その喜びを周囲の人にも分けるため、品物を贈ったり宴会を開いてもてなすこと」が内祝いのもともとの意味です。
しかし近年は、いただいたお祝いに対するお返しの意味で「内祝い」という言葉を使うことがほとんどでしょう。
「お返し」という言い方は直接的であり、やや義務的なニュアンスも含みます。
特に年配の方へ贈るときは「内祝いをお贈りします」と表現するほうが好印象でしょう。
▶GIFTA 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
出産祝いのお返し金額、相場は「半額~1/3」の範囲
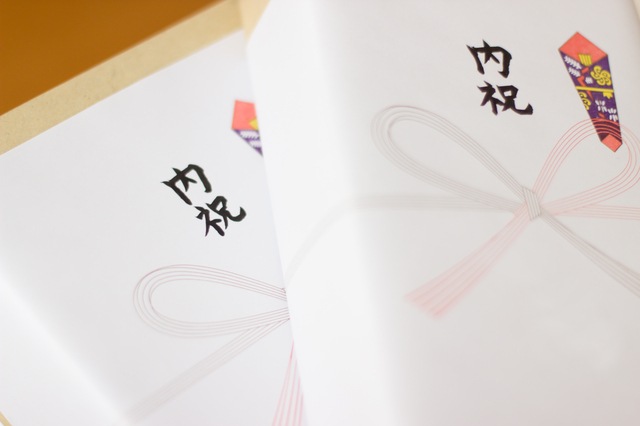
出産祝いのお返し相場は、「いただいたお祝い金額の1/3~半額(半返し)」とされています。
たとえば、2万円の出産祝いをいただいた場合、お返し金額は1万円~7,000円程度の範囲で決めることになります。
「1/3~半額」だと、金額に幅があるため、どちらにするか決めにくいことも。
迷ったときは「一般的な相場は半返し」と考えておけば失敗はないでしょう。
「半額にするか、1/3にするか」の具体的な判断は、お祝いをくださった方との関係や、いただいたお祝い金額なども踏まえて検討するのがおすすめです。
以下で「関係性ごとの出産祝いお返し相場」を解説しますので、自分のケースに当てはめて参考にしてください。
【兄弟姉妹へ】出産祝いのお返し金額は年齢も考慮

兄弟姉妹から出産祝いを贈られたとき、お返し金額の相場は「自分より年上か年下か」で変わります。
兄弟姉妹からもらう出産祝いの相場は、一般的に10,000円~30,000円。
それに対するお返しの目安は、兄姉へ贈るなら「1/3返し」、弟妹に贈るなら「半返し」です。
これは、「目上の人や年上の方には甘えさせてもらってもいいが、自分と同年代やそれ以下の相手には手厚くお返しする」という贈答マナーに基づきます。
年齢差なども考慮しつつ、相手が恐縮しない範囲で内祝いの予算を決めましょう。
【両親へ】出産祝いのお返し金額は相場より少ないことも

親から子へ贈る出産祝い相場は高めで、一般的に30,000円~100,000円といわれます。
中には実家の両親が、
「祖父母として孫の誕生を盛大に祝いたい」
と、相場をはるかに超える高額なお祝いを贈るケースも珍しくないようです。
それに対するお返しは「世間の相場通りでなくとも問題ない」「相場より低めでもOK」という見方が一般的です。
その理由は、親から子へ出産祝いを贈る背景には
「赤ちゃんの育児に役立ててほしい」
「子ども夫婦を援助したい」
という気持ちがあるためです。
こうした親の心情を汲まずに世間一般と同じ半返しをすると、
「あなたがたのお世話にはなりません」
という意思表示に取られかねません。
せっかくお祝いを奮発してくれた両親にさびしい思いをさせてしまうかもしれないのです。
また、 10万円以上の高額な出産祝いへのお返しは、1/3よりさらに低めでもかまわないとされます。
中には両親から,
「出産祝いのお返しは不要だよ。お金は子どものためにとっておきなさい」
と言われるケースもあるようです。
もしその厚意に甘えてお返しを贈らないと決めたなら、代わりに手紙を送るなど感謝の気持ちを言葉にしてしっかり伝えることを忘れないでくださいね。
▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
【親戚へ】出産祝いのお返し金額は年齢・付き合いの深さで判断

おじやおば、いとこなどの親族から贈られる出産祝い相場は、5,000円~10,000円程度が一般的です。
親戚から出産祝いをもらったら、お返し金額は、目上の親族には「1/3返し」、年下の親族には「半返し」と考えるとよいでしょう。
中には、いつも可愛がってくれている高齢のおじやおばから、相場以上に高額なお祝いを贈られるケースもあります。
そんなときは「世間並みのお返しをしなければ」と背伸びする必要はなく、1/4程度のお返しに抑えても問題はないでしょう。
年長者からのご厚意をありがたく受け取り、甘えさせていただくのは、先方の顔を立てることにもつながるので、決して失礼には当たりません。
また、以前、出産祝いを贈ったことがある親族からお祝いをいただいた場合は、その時やりとりした金額に合わせましょう。
▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
【友達へ】出産祝いのお返しは「前にもらった金額」も参考に

友人間で贈る出産祝いの相場は3,000円~10,000円程度。
お返し金額は「いただいた金額の半返し」が目安ですが、日頃のお付き合いの深さによって、調整するといいでしょう。
以前に出産祝い・内祝いのやり取りをしたことのある友人なら
「お相手からもらった内祝いの金額と同等にしておく」
という判断でOKです。
【上司・同僚へ】出産祝いのお返し金額は周囲に合わせることが大事

職場の上司や同僚から出産祝いをもらったら、お返し金額の目安は、上司に「1/3返し」、立場に差がない同僚・部下には「半返し」が一般的です。
目上の方からお祝いをいただいたら、お返し金額を相場の範囲でやや少なめ(1/3返し)にして甘えさせてもらうぐらいでちょうどいいといわれています。
目上の人へ「しっかりお返ししなければ」と半返しすると、場合によってはかえって不相応な対応と受け取られかねません。
例外として、上司が自分と同世代か年下なら、半返しにしても問題はないでしょう。
職場における注意点として、「社内では個人のお祝いごとに関する贈答を禁止する」などの独自ルールがないかを確認しておきましょう。
社歴の長い人などに、今までの様子をそれとなく聞いておくことをおすすめします。
職場の一員として、周囲と足並みをそろえた対応を心がけましょう。
▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
お返し金額はいくら? 迷う事例①「もらった出産祝いが連名だった」

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
職場や友人グループから連名の出産祝いを贈られることもあるでしょう。
連名で出産祝いをもらったら、誰からのお祝いなのかを必ずチェックし、一人ひとりに感謝の気持ちを伝えることが大切です。
「包まれていた金額(もしくは出産祝いの品の金額)を連名人数で割った、一人あたりの金額」を出し、それを基準に半返し(関係性によっては1/3返し)の金額でお返しするとよいでしょう。
注意点として、職場などの大人数で取りまとめたお祝いは、1人あたりのお返し金額が数百円程度の少額になってしまうこともあります。
だからといって何もお返しをしないのはよくありません。
この場合は、お菓子の詰め合わせセットなどをお返しとして贈り、職場のみなさんで分けてもらうなどの対応も可能です。
分配しやすいよう、個包装されたスイーツセットなどを贈るのといいでしょう。
「子供の誕生を祝ってくださりありがとうございます」という感謝の気持ちが、一人ひとりにきちんと届くように伝えることが大切です。
<三浦先生からのひとこと>
連名でお祝いを包んだ場合、祝儀袋の中に別紙を同封し、お祝いを出した人の氏名・住所・金額を記載する習わしがあります。
最近は各人が出した金額まで記載するのは稀になりましたが、金額が書いてあり、人によって差がある場合には、その金額に応じてお返しするようにしましょう。
お返し金額はいくら? 迷う事例②「出産祝いの値段が不明」

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
出産祝いを現金ではなく品物でもらった場合、その価格がわからないと、お返し金額を決めるのに迷いますよね。
価格を知りたくても、贈り主に直接尋ねるのはNG。
市販されている品物なら、インターネットで調べたり店舗に問い合わせたりすれば、おおよその価格がわかります。
その金額を元に、半返し(関係性によっては1/3返し)の金額でお返ししましょう。
また、贈り主自身が手作りした品を出産祝いにいただくケースもあります。
ハンドメイドの品を贈り物にするからには、その方は技術に自信があるものと思われます。
こちらが
「手作り品ならあまりお金が掛かっていないだろうから、お返し金額も安めでいいかな?」
という考えで対応すると、先方に失礼になるかもしれません。
お返し金額を決めかねる場合は、1,000円~3,000円位を目安に、お相手が気を使わない程度のお返しを贈り、感謝を伝えましょう。
お返し金額はいくら? 迷う事例③「出産祝いが現金+品物だった」

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
出産祝いに現金と品物を組み合わせてもらうこともあるでしょう。
その場合のお返し金額は、「両方を合わせた総額」の半返し(または1/3)が相場です。
例えば、現金と品物の合計が2万円であれば、お返しは7,000円~10,000円程度で選ぶことになります。
品物の価格がわからないときは、相手に直接確かめることは避け、インターネットや実店舗でそれとなく類似商品をリサーチしてください。
どうしてもわからないときは、現金分のお返しにやや色を付けて上乗せした金額にしましょう。
お返し予算が決まった! 出産内祝いの贈り方マナーを確認

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
お返しを贈るタイミング
出産祝いのお返しとして内祝いを贈るタイミングは、生後1カ月頃に行う「お宮参りを終えてすぐ」が基本です。
それ以降に出産祝いをいただいた場合は、「お祝いをいただいてから1カ月以内」にお返しすると考えておけば問題はないでしょう。
とはいえ、出産後は生活リズムがガラリと変わって慌ただしい時期。しばらく母子の体調がすぐれないケースもあります。
そんなときは「早くお返しを贈らないと」と無理をする必要はありません。まずは体調を整えることを優先しましょう。
なお、遅れてもお返しの金額を相場以上に上乗せする必要はありません。
出産内祝いを贈る時期や、関連するマナーについては、以下の記事で詳しく解説しているので、そちらもあわせてご覧ください。
出産内祝いに不向きの品・注意点を知っておこう

出産祝いのお返しの品は、予算に合うギフトなら何でもよいというわけではありません。
特に慶事(おめでたいお祝い事)のお返しには不向きとされるものの例をご紹介します。
- 現金(相手の経済状況を心配していると取られることも)
- ハサミや包丁、ナイフなどの刃物(縁切りを連想させるため)
- ハンカチ(手巾という別名が手切れを連想させるため)
- くし(苦と死を連想させるため)
特に年配の方ほど「縁起が悪い」とされてきたものを気にする傾向があります。
縁起を気にせず、実用的なものを喜ぶお相手なら問題ありませんが、できれば上記のような品は避けたほうが無難でしょう。
洗剤は、内祝いに不向きの品とまでは言い切れませんが、「NG」「OK」両方の捉え方があります。
- 「水に洗い流す=喜び事が流れてしまう」ことから慶事によくない(しかし快気祝いにはよい)
- 消耗品だから喜ばれる(一方で消え物はよくないという意見もある)
このように解釈が分かれる品は、相手との関係性を踏まえて適切に判断しましょう。
食べ物を内祝いで贈る場合は、見た目の華やかさに加え、原材料が明記された品質の良い物がおすすめ。さらにお相手にアレルギーがないかも確認できればより安心です
▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
出産祝いのお返しには必ずのし紙を
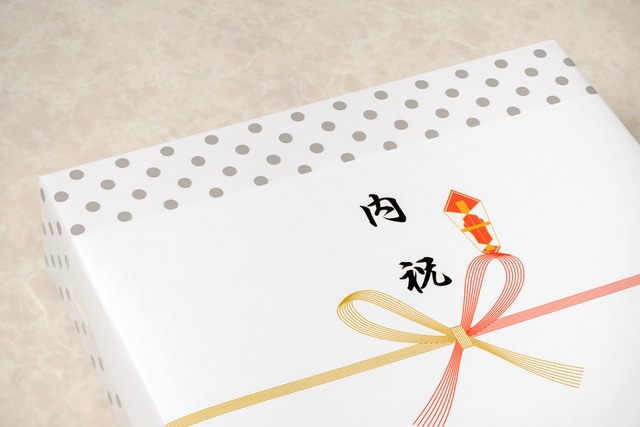
▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
出産内祝いで大切なのは、贈答マナーに沿って感謝の気持ちを伝えることです。
贈り物には必ず「のし(熨斗)紙」を掛けてください。のし紙はお相手に礼を尽くす姿勢をあらわし、贈り物が正式な贈答品であることを示します。
とくに、出産内祝いの品に掛けるのし紙は、「赤ちゃんの名前のお披露目」も兼ねているため、のし紙の書き方が他の贈答品とは異なる部分があります。
必ず正しい書き方を確認してください。
また、のし紙には複数の種類があり、目的によって使い分けることも必要です。
出産内祝いの「のし」のマナーについては、以下の記事で詳しく解説しているので、そちらもあわせてご覧ください。
<三浦先生からのひとこと>
出産内祝いののし紙の最大の特徴は、水引の下の名入れ部分に「苗字を入れず赤ちゃんの名前だけ」を書くことです。
最近は読み方で迷わないよう、読み仮名をつけることも多くなりました。
出産祝いをくださった方々に赤ちゃんの名前を披露する意味があるので、親の名前を書いたりしないよう注意してください。
出産祝いのお返し金額を軽減! リーズナブルな選び方

出産内祝いは、お祝いをくださった方々へ一斉にお返しすることがほとんど。
そのため、一時的に出費がかさみ、家計を圧迫してしまうことも珍しくありません。
出産祝いのお返しをできるだけリーズナブルな金額で用意したいなら、「割引価格」「まとめ買いサービス」のあるギフトショップやモノを選ぶのがおすすめです。
その点、重宝するのが「カタログギフト」。
一部のギフト専門店ネットショップでは「割引カタログギフト」の販売や「カタログギフトのまとめ買い割引」を実施しています。
インターネットのギフト専門店・GIFTA(ギフタ)でも「割引カタログギフト販売」や「まとめ買い割引適用」を行っています(※一部対象外商品あり)。
「家計への負担を減らしながら、お返し予算よりも実質ワンランク上の贈り物ができた」
と大好評。
出産祝いのお返しにカタログギフトを検討されるなら、ぜひ当店のECサイトをチェックしてください。
内祝いを買うギフトショップは「送料割引サービス」の有無をチェック

お返し品そのものの金額だけでなく、件数が増えるごとに配送料もかさみます。
ここは上手にやりくりしたいところ。
特に一人あたりのお返し品が少額の場合は、
「品物代より配送料のほうが高くついてバランスが悪い」
ということになりがちです。
内祝いを購入するギフトショップ選びは、まず「送料の割引サービスがあるかどうか」を判断基準にすることをおすすめします。
ただし、「●円以上ご購入の場合」など条件付きのことが多いので、しっかり確認してください。
GIFTA(ギフタ)でも、お届け先1件当たり一定金額以上のご購入で、送料無料サービスを行っています。
ぜひECサイトをのぞいてみてください。
▶GIFTA はお買い上げ金額により送料無料も! くわしくはこちら
ネット直販で出産祝いのお返しがスムーズに

▶ギフタ はお買い上げ金額により送料無料も! くわしくはこちら
出産直後は赤ちゃんのお世話で忙しくなります。
また、ママさんの体調が整うのに時間がかかることもあるでしょう。
「デパートに行ってお返しの品選びをするなんて、時間的にも体力的にも無理」
「出産内祝いに添える挨拶状は、どうしたらいいんだろう……」
とお悩みの人がほとんど。
気づけばお宮参りの日を迎え、「内祝いの準備を急がなきゃ!」と焦ることも。
そんなときはギフト専門店のネットショップを利用して、お返しの品をスマートに手配してしまいましょう。
内祝いを贈る方をリストアップしておき、送り先の住所や連絡先をまとめておくと、配送手配がスムーズにできます。
複数の方にすぐにお返しを贈りたいとき、ギフト専門店・GIFTA(ギフタ)なら、スマホひとつで全員分の内祝いをまとめて手配できます。
一定金額以上のご購入で送料無料。
もちろん、のし紙の記入・挨拶状の作成も無料サービスです(※一部対象外商品あり)。
さらに、挨拶状に赤ちゃんの写真を入れるサービスも行っています(※一部対象外商品あり)。
GIFTA(ギフタ)の運営母体は、各種挨拶状の印刷サービスを行うネットショップ「おたより本舗」。
印刷会社の技術を生かし、高画質の写真入り挨拶状を作成できるのがGIFTA(ギフタ)の特長です。
可愛い赤ちゃんの写真入り挨拶状がスマホ上で作成できるので、ぜひGIFTA(ギフタ)の出産内祝いサイトをチェックしてみてください。
▶写真入りも簡単☆ギフタのメッセージカード(無料)デザイン一覧はこちら
出産祝いのお返しに! 金額別の人気ギフト紹介【専門店おすすめ】

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
ここからはネット直販のギフト専門店GIFTA(ギフタ)のおすすめ商品をご紹介します。
お返し選びで大切なのは、お相手との関係性や好みを踏まえること。
例えば、両親や祖父母なら、赤ちゃんの写真や名前の入った記念品が喜ばれるでしょう。
その一方で、同僚や友人に贈るなら日用品や食品など、後に残らない「消え物」がおすすめです。
【予算1,000円~3,000円】出産内祝いの例

3,000円未満の予算でまかなう出産内祝いの定番といえば、お相手に気を使わせない「消えもの」です。
消えものでおすすめなのは、家族や仲間と気軽に味わえる「焼き菓子の詰め合わせ」、リラックスタイムを演出する「入浴剤のセット」など。
忙しい人には、お湯をかけるだけでスープや味噌汁が用意できる「高級フリーズドライ食品」、子どもがいる家庭に贈るのであれば「高級ジュースの詰め合わせ」なども喜ばれるでしょう。
消えもの以外では、何かと助かる「高級ブランドのタオルギフト」なども選択肢に入ってきます。
【予算5,000円~10,000円】出産内祝いの例

出産内祝いに5,000円~10,000円程度の予算をかけるときは、自分ではあまり購入しない特別感のある品物やリッチ感のあるものなどがおすすめ。
お肉が好きな人には「高級和牛」や「お肉ギフトの詰め合わせ」などを贈って味わってもらいましょう。
10,000ほどの予算があれば、上質なお酒も選択肢に入ってきます。
お酒が好きな方への内祝いには、おめでたい意味をこめた「紅白ワインセット」や、お祝いごとに欠かせない「日本酒」もおすすめです。
家族全員で食べられるものなら、温めるだけでいい有名ホテルの「スープセット」や「レトルト食品」「高級スイーツ」などもチェックしてみてください。
▶ギフタ 5,001円~10,000円の出産内祝い一覧ページへ
【予算10,000円~30,000円】出産内祝いの例

10,000円~30,000円程度の高額な出産内祝いとなると、金額が高い分、お相手に喜んでもらえるものを外さずに選びたいですよね。
先方の好みがわからず迷うときは、「内祝い向きカタログギフト」を贈るのもおすすめです。
カタログギフトの魅力は、贈られた人が欲しいものを探しながら選ぶワクワク感も味わえるところ。
近年はカタログギフトの種類が豊富になり、さまざまなコンセプトで編集されたものが登場しています。
- 幅広いジャンルの品物を扱う「総合カタログ」
- 全国から集めた選りすぐりグルメに特化したカタログ
- 有名雑誌とコラボし、おしゃれな雑貨を集めたカタログ
- ネット通販で手に入る上質な割引カタログギフト など
ギフト専門店ならサイト内に電子カタログを用意してあります。気になるカタログギフトの中身を購入前に閲覧できるので安心ですよ。
連名のお祝いにはプチギフトや詰め合わせのお返しを

職場の同僚たちから連名の出産祝いをいただいた場合、一人あたりのお返し金額が1000円以下の少額になることもあります。
少額でも、祝ってくれた一人一人にお返しするのが基本的なマナー。
しかし、それほどこだわらなくてもいいなら、詰め合わせギフトを職場に持参し、みんなで分けてもらうといいでしょう。
その場合は、分けやすいように個包装のものを選んでくださいね。
人生の節目の出産内祝い、失礼のないお返しを

▶ギフタ 出産内祝いに好評★ かわいいデザインのし紙(無料)一覧ページはこちら
親族や友人、職場の方から出産祝いをいただいたら、お返しとして出産内祝いを贈るのがマナーです。
お返し金額の一般的な相場は「いただいた出産祝いの金額の1/3~半額」といわれています。
自分よりも目上の方には「1/3返し」で、お返しを少なめに抑えて甘えさせていただいてもOK。そのほうがかえってお相手の顔を立てることにもつながります。
一方、自分と同年代や下の立場の人へは「半返し」にし、余裕のある対応を心がけましょう。
実家の両親から、相場を大きく上回る高額な出産祝いを贈られた場合は、無理に相場に合わせなくても問題ありません。
上記のように、お返し予算は、いただいたお祝いの金額と関係性に応じて、バランスを見ながら決めましょう。
赤ちゃんが生まれ新しい家族が増えることは、夫婦だけでなく周りの人にとってもうれしいこと。
人生の大切な節目なのでマナーに沿った対応を心がけ、祝福への感謝をしっかり伝えましょう。