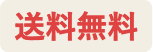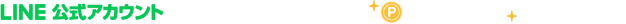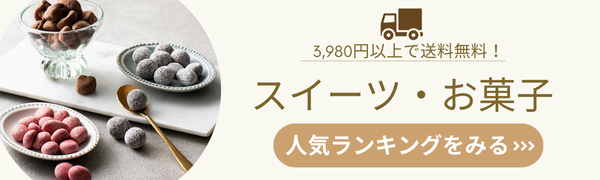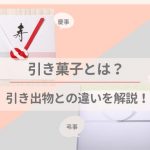冬季限定のスイーツがあるように、寒い時期だからこそ食べたくなるスイーツがありますよね。
今回は季節を感じてもらえる冬スイーツの魅力を一挙にご紹介します。
リラックスタイムに自分で味わったり、誰かにプレゼントしたりするときの参考にしてください。
冬に食べたいスイーツ【洋スイーツ編】

生クリームやチョコレートが溶ける心配のない冬は、洋スイーツのおいしさが引き立つ季節。
温めて味わうスイーツなら、心も体も温まりますよね。
まずは、「洋の冬スイーツ」を紹介します。
ぜひお気に入りを見つけてみてください。
フォンダンショコラ

「フォンダンショコラ」は、チョコレートクリームが入ったチョコレートケーキのこと。温かい状態で食べるスイーツなので、寒い冬にぴったり!
「フォンダン」とはフランス語で「溶ける・やわらかい」という意味。その名のとおり、ナイフを入れると中からチョコレートクリームがとろりとあふれ出します。
大切な人とのひとときや自分へのごほうびタイムに味わってみましょう。チョコレートの甘い香りがふわりと広がって、心を解きほぐしてくれますよ。
ガトーショコラ

「ガトーショコラ」は、フランスで誕生したお菓子で、直訳すると「チョコレートの焼き菓子」です。
日本では、チョコレートやココアパウダーをふんだんに使ったチョコレートケーキのことを指すのが一般的です。
濃厚なチョコレートの風味としっとりした食感がおいしいスイーツで、子どもから大人まで幅広い世代に人気。
ちょっとしたパーティーからほっとひと息つきたいときまで、さまざまなシーンに合います。
生チョコレート

「生チョコレート」は、生クリームを練り込んで作るチョコレートのことです。
一般的なチョコレートと違ってしっとりやわらかく、口に入れた瞬間にとろける独特の食感が楽しめます。
生チョコレートは高温に弱く溶けやすいため、外で持ち歩いたりプレゼントしたりするなら冬がおすすめ。
市販されている生チョコレートは、一口大にカットされている商品や個包装されているものが一般的です。
手軽に食べられる形なので、甘いものをつまみたいときや休憩時間のおやつにぴったりです。
モンブラン

栗の入ったピューレを細い紐状にして盛り付ける「モンブラン」。正式名称は「モン・ブラン・オ・マロン」といいます。
モンブランとはフランス語で「白い山」という意味。名前の由来は、アルプス山脈にある標高4,807mのモンブラン山という説が有力です。
こんもりとした形や白い粉砂糖が、雪の積もった山を思わせる、見た目からして冬にぴったりのスイーツです。
アップルパイ

甘く煮たリンゴを、パイ生地にたっぷり詰めて香ばしく焼き上げる「アップルパイ」。アメリカのスイーツという印象がありますが、元々はイギリスで誕生しました。
アメリカでは、イギリスから移り住んだ人々が現地で育てたリンゴでアップルパイを作ったことから広まったといわれています。
リンゴは秋から冬にかけて旬を迎えるので、おいしいリンゴをたっぷり使ったアップルパイを食べたいなら、冬がおすすめ。
アツアツのアップルパイは、体も心も温めてくれるでしょう。
チーズケーキ

「チーズケーキ」は、チーズを使って作るケーキの総称。レシピや作り方によって違ったテイストになるスイーツなので、さまざまな種類があります。
代表的なスタイルは、キツネ色に焼き上げる「ベイクドチーズケーキ」、火を通さずに作る「レアチーズケーキ」、湯煎してじっくり焼く「ニューヨークチーズケーキ」など。
近年は、スペイン発祥で真っ黒い焼き目が特徴の「バスクチーズケーキ」も人気!
男性の中には「甘いものはあまり食べないが、チーズケーキだけは食べやすくて大好き」という人もいるようです。
ちょっとした集まりの手土産や子どものおやつにもおすすめ。
いろいろな種類を食べ比べてみて、好みの味を見つける楽しみも味わえるでしょう。
バウムクーヘン

「バウムクーヘン」は、ドイツで生まれた伝統的なスイーツです。
日本語に訳すと「木のケーキ」という意味で、木の年輪を思わせる断面が大きな特徴。
棒状のローラーに生地を塗ってゆっくりと回転させながら焼き上げ、焼き目が付いたらその上にまた生地を塗って焼くという行程を何度も繰り返して作られます。
年輪を思わせる何層にも重なった見た目が「長い年月を重ねていくシンボル」とされ、”縁起のよいスイーツ”としても知られています。
結婚式の引き出物やプレゼントとして人気があるほか、誕生日のお祝いやクリスマスにもぴったりです。
ショートケーキ

「ショートケーキ」は、誕生日やクリスマスによく食べられている定番スイーツの一つ。
日本では、「イチゴの乗った生クリームのケーキ」というイメージが定着しているものの、本来はクリームをあしらったスポンジケーキやビスケット全般を指します。
アメリカではサクッとしたビスケット生地を使うのに対し、日本ではふわふわのスポンジを使うことで独自の進化を遂げました。
お祝いごとや特別な日に欠かせないスイーツです。
ロールケーキ

薄いスポンジ生地でクリームやジャムを巻いて作る「ロールケーキ」。発祥には諸説ありますが、1880年代の終わり頃に「スイスロール」として紹介されたものという説が有力です。
生地やデコレーションのバリエーションが多く、カットしたときに現れる渦巻き状の断面に食欲をそそられる人も多いでしょう。
冬のロールケーキといえば、フランスのクリスマスケーキとして知られる「ブッシュ・ド・ノエル」です。木をかたどった素朴なデコレーションが、クリスマス気分を盛り上げてくれます。
シュトーレン

「シュトーレン」とはドイツに伝わる伝統的なクリスマスのスイーツです。
パン生地の中にドライフルーツやナッツを入れ、表面に粉砂糖をまぶして作ったものが一般的ですが、使う食材や作り方は地域やお店によって異なります。
時間が経過するにつれてドライフルーツの味が生地に染み込み、味が変わってくるのが魅力。
本場ドイツではクリスマスの4週間前から少しずつスライスして食べます。
自宅で楽しむおやつに取り入れて、本場のクリスマス気分を味わってみてはいかがでしょうか。
マカロン

写真映えするかわいい「マカロン」はイタリア生まれのスイーツ。
16世紀にフランスへ伝わり、フランス各地でさまざまなタイプのマカロンが作られるようになったといわれています。
コロンとした丸い形に、クリームやジャムを挟んだ定番のスタイルは、パリで生まれたもの。
おいしいだけでなく、カラフルな見た目も楽しめるマカロンは、おしゃれな女性へのプレゼントやちょっとしたお礼にもおすすめです。
焼き菓子ですが、崩れやすい卵白生地に溶けやすいクリームがサンドしてあるため、冬の方が繊細な食感をしっかりと楽しめます。
カヌレ

「カヌレ」は正式名称を「カヌレ・ド・ボルドー」といい、発祥はフランスのボルドー地方にある修道院だといわれています。
「カヌレ」とは「溝の付いた」という意味。名前の通り、凹凸のあるつりがねの形をしたカヌレ型を使って作られます。
表面はカリカリで香ばしく、中身はしっとりとした食感で、小さくても満足感たっぷり。カットする必要のない食べやすいサイズ感は、大人数が集まるパーティーへの差し入れやギフトにも重宝するでしょう。
ワッフル

素朴な甘さが楽しめる「ワッフル」。
日本で販売されているのは主に、カリッとした食感の「ベルギーワッフル」と、ふんわりした「アメリカンワッフル」の2種類です。
両者の違いは、発酵方法にあります。
ベルギーワッフルは、イーストで発酵させるのに対し、アメリカンワッフルはベーキングパウダーを使用しているのがポイント。
さらに、ベルギーワッフルには、長方形で甘さが抑えめの「ブリュッセルワッフル」と形が丸くて甘い「リエージュワッフル」があり、意外と奥が深いスイーツ。
「ブリュッセルワッフル」はクリームやフルーツをトッピングして、「リエージュワッフル」はシンプルにそのまま食べるスタイルが定番です。
エクレア

細長い形が特徴の「エクレア」のネーミングは、フランス語の「エクレール(稲妻)」が由来。
「生地の表面にできる亀裂が雷に見える」「中のクリームが飛び出さないよう稲妻のように素早く食べる必要がある」などの説があります。
分類としてはシュークリームの一種ですが、細長いぶんシュークリームよりも食べやすく、カフェタイムのおやつにぴったり。
表面にはチョコレート、中にはクリームが入っているため、持ち運ぶなら冬がおすすめ。溶けないうちに味わいましょう。
アイスクリーム

ひんやりとした食感がおいしい「アイスクリーム」。一見すると夏のスイーツのように感じられがちですが、「暖房が効いている室内で食べるのが好き」という人は意外にも多くいます。
日本の規格で「アイスクリーム」に分類されるのは、乳固形分15%以上、うち乳脂肪分8%以上のもの。それ以下の割合になると「アイスミルク」や「ラクトアイス」に分類されます。
冬に濃厚なミルクの味わいを楽しみたいなら、ぜひ「アイスクリーム」を選びましょう。栄養も豊富なので、食後のデザートやおやつのほか、食欲がないときにもおすすめです。
夏場なら、フルーツソースやはちみつをトッピングすることが多いアイスクリーム。
冬に楽しむなら、アツアツの濃いコーヒーをかけていただく「アフォガート」もおしゃれな味わい方ですよ。
\売れ筋商品をチェックしたい方はこちら/
冬に食べたいスイーツ【和スイーツ編】

寒さが厳しい冬には、熱い緑茶やほうじ茶が恋しくなりますよね。
そんなときお茶と一緒に味わいたいのが、やさしい甘さがうれしい和のスイーツです。
冬にぴったりの和のスイーツを紹介します。
ぜんざい・おしるこ

甘く煮たあんこに、お餅や白玉を入れる「ぜんざい」や「おしるこ」は、寒い時期にこそ食べたくなるおやつメニューです。
ぜんざいとおしるこの定義は地域によって異なるのもおもしろいところ。
例えば「おしるこ」は、関東では粒あんもこしあんも使われますが、関西ではこしあんのみ。
また、関東の「ぜんざい」は汁があるのに対して、関西では汁なしというケースも。
旅行に出かけた際は、各地のぜんざいやおしるこを食べ比べてみるのも楽しそうですね。
小腹がすいたときやひと息つきたいときに味わえば、あんこの甘さが身も心も温めてくれるでしょう。
栗菓子

栗を使った「栗菓子」には、「栗きんとん」「栗まんじゅう」「栗かの子」「栗ようかん」などさまざまな種類があります。
いずれも栗のほのかな風味を生かした上品な味わいが魅力で、年配の方への手土産にもぴったり。
岐阜県・美濃地方の名物として知られる「栗きんとん」は、おせち料理に使う栗きんとんとは違い、すりつぶした栗を茶巾絞りにするスタイル。
栗菓子は栗が旬を迎える秋から冬にしか販売しない店舗も多く、冬期にぜひ味わっておきたいスイーツです。
抹茶菓子

抹茶をふんだんに使った「抹茶菓子」は、日本人にとって身近な和菓子の一つです。
「抹茶カステラ」や「抹茶どらやき」「抹茶豆」など、抹茶のテイストは近年になっていろんなお菓子に取り入れられ、広がりを見せています。
抹茶は和菓子だけでなく、チョコレートやクッキー、フィナンシェなど洋菓子の風味づけにも使われることが増えました。
お茶の風味がメインの抹茶菓子は、温かい緑茶やほうじ茶などと相性がよく、お茶請けにぴったり。
使われる抹茶の量が増えるほど苦味も増して、大人っぽい上品さを感じさせる味になります。
ギフトで贈るなら相手の好みに合わせたものをチョイスしましょう。
かりんとう

「かりんとう」は、棒状にした一口大の生地を油で揚げ、砂糖をまぶしたお菓子です。
いつごろ誕生したのか、明かではありませんが、庶民の口に入るようになったのは明治時代のこと。
時代が進むにつれ多くのバリエーションが生み出され、黒砂糖を使ったシンプルなもののほか、抹茶味・キャラメル味・メープル味・野菜味なども誕生しています。
軽い食感と甘さがおいしく、温かいお茶でほっとひと息つくティータイムのおやつや、贈り物としても大活躍するスイーツです。
芋けんぴ

サツマイモを細長く切り、カラッと揚げて砂糖蜜をたっぷりかける「芋けんぴ」は、高知県の銘菓としてよく知られています。
サツマイモの甘さと砂糖の甘さが生み出す素朴な味わいと、カリカリの食感が魅力。使われるサツマイモの種類やカットする際の太さによっても味わいが変わります。
片手でつまめることもあって、食べ始めると止まらなくなることでしょう。
サツマイモが旬を迎える冬にこそ味わいたいスイーツです。
たいやき

あんこをたっぷり詰めて、魚のたいの形に焼き上げる「たいやき」は、明治時代に誕生したスイーツです。
時代を経て、あんこではなくチョコレートやカスタードクリームを詰めたものなど、味のバリエーションが広がりました。
近年は、生地にもお店の工夫がこらされるようになり、クロワッサン生地を使ったたいやきも人気を博しています。
長年変わらないユーモラスな形は、どこから食べるかという話のネタにもなります。
できたてのたいやきはアツアツで、両手で持ってほおばれば寒さを忘れさせてくれるに違いありません。
ちょっとした手土産や小腹がすいたときのおやつにぴったりです。
どらやき

円形をした2枚の生地であんこを挟んだ「どらやき」。
名前の由来は「楽器の銅鑼(どら)の形を模した」「熱した銅鑼を使って焼いた」などの説があります。
シンプルなお菓子ゆえにアレンジがしやすいのが特徴。
栗を入れた栗どらやきの他、チョコレートクリームや生クリームを挟んだ変わりダネどらやきなど、さまざまな味の商品が登場しています。
熱いお茶との相性は抜群。お箸やフォークいらずで、片手でパクッと食べられるのもうれしいポイント。
個包装されているものが多いため、ギフトにも最適です。
串だんご

米粉を使っただんごを、串に刺して味を付ける「串だんご」は、ほっとひと息つきたいときのお茶請けやおやつにぴったりのお菓子です。
甘いタレのかかった「みたらし団子」をはじめ、花見団子とも呼ばれる「三色団子」、きな粉やあんこをトッピングしたもの、のりで巻いたものなど、種類やアレンジも豊富に揃っています。
できたてでホカホカのだんごは、寒い冬こそよりいっそうおいしく感じられる和スイーツ。手を汚さずに食べられる点も高ポイントですね。
大福

お餅であんこをくるむ「大福」は、江戸時代に誕生したといわれています。
冬に食べたい大福といえば、あんこと一緒にイチゴをくるんだ「イチゴ大福」です。
旬を迎えたイチゴの甘さと酸っぱさがあんこと合わさり、絶妙な味わいを楽しませてくれます。
さらに近年はイチゴ以外のフルーツを使った「フルーツ大福」も登場し、かわいい見た目と新鮮なおいしさで人気に。
注意点としては、日持ちしないので、ギフトで贈る場合は冷凍タイプを選ぶのがおすすめです。
カステラ

「カステラ」は、16世紀にポルトガルの商人や宣教師によって長崎県に伝えられたといわれるお菓子です。
その後、日本人の手によってレシピや作り方が工夫され、400年以上の歳月を経て和菓子として定着しました。現在も長崎県の銘菓としてよく知られています。
ふんわりした生地とザラメの甘さが温かいお茶や紅茶と相性抜群。
子どもから大人にまで世代を超えて愛されるカステラは、手土産やギフトにもぴったりです。
あらかじめカットされているタイプだと切る手間が省けます。
八ッ橋

ニッキ(シナモン)を混ぜた生地を焼き上げた「八ッ橋」が誕生したのは、江戸時代のことです。
「琴の形を模して作られた」「伊勢物語を偲び、作中に登場する八橋という地名から作られた」といった説があります。
現在は京都のおみやげとして有名に。その上品で素朴な味わいは熱いお茶のお供にぴったりです。
生地を焼かないものは「生八ッ橋」として区別されています。
\ギフト専門店の豊富なラインナップを見る/
冬のスイーツを知って喜ばれるギフトを贈ろう

冬に旬を迎えるフルーツを使ったものや、クリスマス向けのスイーツなど、季節を感じられるスイーツは贈り物にぴったり。
寒い季節だからこそ、あつあつのデザートやチョコレートをたくさん使ったスイーツは、よりおいしさが引き立ちます。
季節の美味しいスイーツで、大切な人や身近な人に笑顔をおすそ分けしてくださいね。
\送料無料スイーツも多数!/