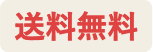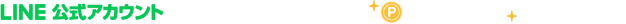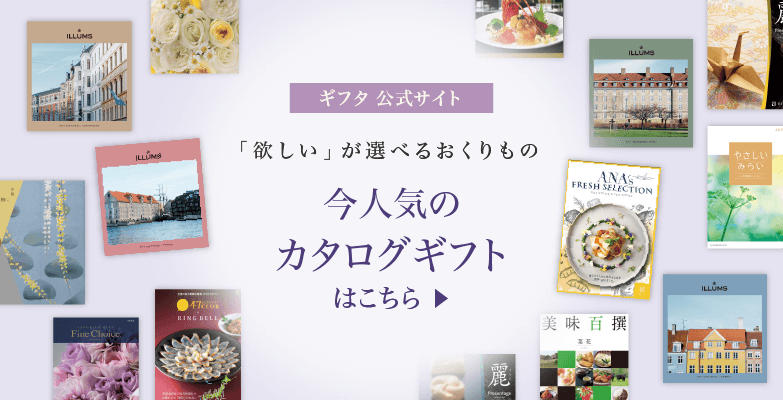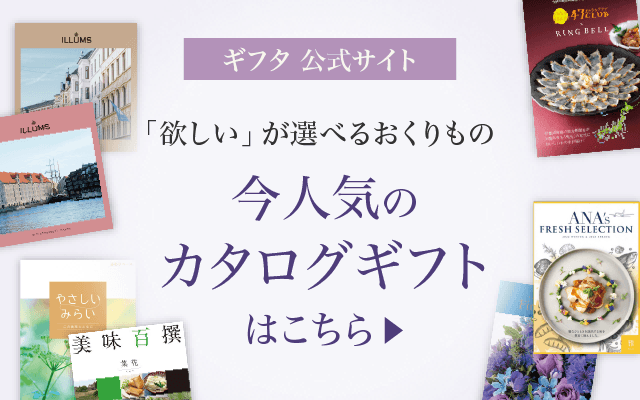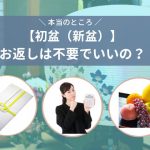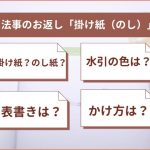大切な方の喪中に迎えるお正月。
「毎年恒例のおせち料理を食べても大丈夫?」
と気になっている方もいるのではないでしょうか。
故人の死を悼み、喪に服す期間である喪中は、年末年始の準備や過ごし方もいつもとは違います。
喪中に「食べてはいけないもの」「してはいけないこと」を正しく理解して、故人を偲ぶお正月を過ごしましょう。
目次
喪中におせちを食べない理由

喪中のお正月には、おせちを食べないほうがよいとされています。
その理由は、喪中は故人の死を悼み喪に服す期間であり、おめでたいことを避けて過ごすべきと考えられているためです。
また同時に、遺族はこの期間に悲しみを癒すとされています。
新年を祝うおめでたい「おせち」は、喪中の主旨にふさわしくないといえるでしょう。
ただし、宗教によっては、故人が亡くなって最初のお正月も、いつも通り過ごす場合があります。
喪中(および忌中)の考え自体がないキリスト教や浄土真宗では、おせちを食べたり、新年を祝ったりしても問題はありません。
喪中の範囲と期間

ここで、喪中の基本的な知識についておさらいしましょう。
喪中の範囲は、二親等の家族までとされています。
その期間は続柄によって異なり、一般的には、以下の通りとされることが多いです。
- 父母、義父母 12~13か月
- 子ども 3~12か月
- 祖父母 3~6か月
- 兄弟姉妹 1~6か月
このとき、自分が喪中で、配偶者は喪中ではない、ということが起こりえます。
喪中を理由に自分だけ義実家や親族の集まりを断ることは失礼にはあたりませんが、断り切れないこともあるでしょう。
その場合の対応については、次に解説します。
喪中のおせち、縁起物を避けて作るのはOK

喪中におせちを食べることは避けるべきですが、新年を祝う意味の食材を入れずに作るのは問題ありません。
おせちを手作りする場合は、以下を参考に、縁起物の食材を避けるようにしてください。
<喪中には避けたい縁起物>
- 鯛
- 海老
- 紅白のもの(かまぼこ・なますなど)
- 昆布
- 菊や菊をかたどった野菜(かぶなど)
- 大根とにんじんなど、取り合わせると紅白になるものにも注意
また、義実家や親族への訪問を断り切れず、おせちがふるまわれることもあるでしょう。
せっかくの厚意ではありますが、故人を思う気持ちを大切にしたいと考えるなら、縁起のよい食材は避けていただくとよいでしょう。
食べてもよいおせちの具材
一般的なおせちに入っている食材でも、新年を祝う意味合いを持たないものは食べてよいとされています。
手作りのおせちには、こうした食材を使ってみてください。
喪中にも食べられる食材とその意味をご紹介します。
<喪中にも食べられる食材>
- 黒豆…健康でマメに働けるように
- 栗きんとん…「金団」と書くことから、「金運をよぶ」
- ぶり…出世魚であることから、「立身出世」
- 田作り…「五穀豊穣」カタクチイワシが肥料として使われたことから
- 伊達巻…巻物に似ていることから、「知識が身につく」
喪中のおせちは食材以外にも注意
おせちを自作する場合、食器に重箱や祝い箸を使わないようにしましょう。
2段以上に重ねられた重箱には「おめでたいことが重なるように」という縁起のよい意味が込められています。
喪中には不幸が重なることを連想させ、ふさわしくありません。
ハレの日に使われる祝い箸も同様です。
お皿に盛って、いつも通りの食事として食べるとよいでしょう。
また、せっかく手間をかけて作るおせちですが、親戚や友人を招いてふるまうのはやめましょう。
盛大な宴会は避け、家族だけで、静かにお正月を過ごすようにしてください。
喪中におせちの代わりに用意する正月料理

いつものお正月は、おせち料理を購入しているという方も多いはず。
新年を祝う食材を避けるために、今年に限っておせちを作るのは大変です。
そんな方へ、おせちの代わりに用意できる正月料理をご紹介します。
喪中にも食べられる「ふせち料理」
ふせち料理とは、喪中の方が食べられるように考えられた正月料理で、おせちから「新年を祝うおめでたい食材」を除いたものです。
精進料理がベースになっており、喪中の方も安心して召し上がれます。
また、見た目にも華やかになり過ぎないよう工夫がされています。
ふせち料理は、おせちほど手に入りやすくはないですが、仕出し料理のお店などで購入が可能です。
また、最近では大手百貨店などでも肉や魚を使用しない「精進おせち」が販売されており、喪中におせちの代わりとして選ばれているようです。
食べてもよい正月料理|お雑煮、年越しそばはOK

おせち以外にも、年末年始にはさまざまな料理がふるまわれます。
喪中に食べても問題ないか、確認しましょう。
年越しそばは、喪中でも避ける必要はありません。
長寿への願いや厄落としの意味を込めた年越しそばは、新年を祝う意味合いを持たないため、食べてよいとされています。
また、お雑煮も、それ自体は問題ありません。
ただし食材には注意が必要です。
お供えした餅(鏡餅)は、縁起物のため入れないようにしましょう。
紅白のかまぼこや、大根とにんじんなど紅白の取り合わせも避け、白い具材のみ使うようにしてください。
もうおせちを買ってしまった…。という方は食べ方に工夫を

おせちの購入は毎年のことのため、早めに予約購入をしてしまった方もいるでしょう。
その後に「喪中におせちはだめだった」と気がついたら、どう対応すべきか迷いますよね。
結論としては、家族だけで食べる場合、キャンセルする必要はないと考えられます。
喪中であることを考慮し、以下のことに気を配りましょう。
- 重箱から出し、お皿に移す
- 祝い箸を使わない
- 親族や友人を招かず、家族のみで食べる
なるべく祝い事らしさを薄めることを意識し、華やかな飾りなどは取り除いて、いつも通りの食事に近づけてください。
ご近所さんの目に触れるのが気になる場合は、お店や宅配でおせちを受け取る日時なども工夫するとよいでしょう。
おせち代わりにのんびり味わうお取り寄せグルメ
喪中には、おせちや正月料理ではなく、通販でお取り寄せグルメを頼むのもひとつの手です。
お正月は家族がそろって休暇になる、数少ない機会だというご家庭も多いでしょう。
喪中で「新年を祝う」ことができなくても「家族で大切な時間を過ごしたい」と思うものではないでしょうか。
「ふせち」や、縁起物を除いた手作りおせちを準備するのはもちろんよい方法です。
しかし購入できる場所が近くになかったり、買い回りに時間がかかったりすることも考えられます。
買い物や料理を担当する家族は、お休みの間も忙しく動き回ることになりかねません。
その点、お取り寄せなら、買い物や料理に費やす時間を短縮することができます。
久しぶりに家族がそろうお正月に、手間をかけずに上質な料理を楽しめる「お取り寄せグルメ」は、実は最適な選択なのです。
「おめでたい食材」を避けたお取り寄せグルメをご紹介します。
お鍋で体も温まる「お肉」
上質なお肉は、家族が久しぶりに集まるシーンにふさわしい、特別感があります。
とくに「すき焼き」「しゃぶしゃぶ」などの鍋物は、体が温まるうえ、家族で囲む楽しさがあるためおすすめです。
かつては、忌中(故人が亡くなってから四十九日まで)に「四つ足生臭もの」と呼ばれる肉や魚を食べないというしきたりがありました。
そのため「喪中にお肉を食べていいのかな…?」と気になる方もいるでしょう。
しかし、現在では忌中に肉や魚を控えるご家庭はごくまれです。
ご家族の意向に問題がなければ、家族団らんの食事の候補にしてみてはいかがでしょうか。
お正月らしい和食でいただく「魚介」
魚や貝は、鍋や西京焼き、干物、刺身など、和食のお取り寄せグルメに多く使用されています。
魚介をメインにした和食は味も見た目も上品で、家族で静かに過ごすには最適な品といえるでしょう。
お肉料理ではどうしても華やかに感じる、という方にもおすすめです。
品物を選ぶ際は、「鯛」や「海老」「たこ」「かつお」など、おめでたいことを連想させる魚や、慶事の贈り物によく選ばれる魚を避けてください。
時節柄「ぶり」「鮭」「ほたて」「かに」など、旬の食材がとくにおすすめです。
味の趣向を変えて「洋食」「中華」
年末年始はどうしても和食を食べる機会が多くなります。
もちろんおいしいですが、何日も続くと味の濃いものが食べたくなる方も多いでしょう。
お正月休暇の後半には洋食や中華の惣菜を取り寄せて、趣向を変えてみてはいかがでしょうか。
温めるだけで食べられるものを選べば、手軽な調理で本格的な味を楽しめます。
子どものいるご家庭には「ハンバーグ」や「カレー」「飲茶」などのセットがとくにおすすめです。
お正月の家族団らんのお供に「スイーツ」
小さな子どもから大人まで、家族がそろうお正月にみんなで味わいたいのが「お取り寄せスイーツ」です。
最近では、さまざまなスイーツをお取り寄せできます。
- 長年愛される老舗フルーツ店のアイスやケーキ
- 「北海道」のチーズやミルクを使用したスイーツ
- 分けやすく食べ応えのある焼き菓子セット
普段自宅の近くで手に入らない品を楽しめるのは、お取り寄せの醍醐味といえるでしょう。
あまり華やかにしたくないという方は、落ちついた印象の「和スイーツ」を選んでみてはいかがでしょうか。
こうした品は、上品な味わいで年配のご家族にも気に入っていただきやすいでしょう。
喪中のお正月の過ごし方

喪中のお正月は、おせちなどの食べ物以外にも、気をつけるべきことがあります。
たとえば、ご自宅に親戚や友人を招いて盛大なお祝いをするのは避けるべきです。
基本的には、家族と静かに過ごしましょう。
※例外として、故人を偲ぶ目的で親戚などが集まる場合は、開催しても問題はありません。
このほかにも、喪中には控えるべきことがあるため、解説します。
新年のあいさつ・年賀状は控える

「おめでとう」などの新年を祝う言葉は、喪中にはふさわしくありません。
こちらから「あけましておめでとうございます」とお声掛けするのはなるべく避け「今年もよろしくお願いします」などと言い換えるとよいでしょう。
同じ理由で、年賀状を出すのも控えるべきとされています。
喪中で年賀状を欠礼する際には「喪中はがき」で事前にお知らせをするのが通例です。
喪中はがき(時期によっては「寒中見舞い」)については、以下の記事を参考にしてください。
家の前に正月飾りは置かない

「門松」「しめ縄」「鏡餅」など、晴れやかなことを連想させる正月飾りは、喪中には飾らない方が無難でしょう。
本来は四十九日を終えた「忌明け」後には、飾ってもよいとされていますが、実際には飾らない家庭の方が多いようです。
とくに関扉の前に飾る「門松」や「しめ縄」は、近所の方の目に触れるため控えましょう。
「鏡餅」は、ご家庭によっては家の中に飾る場合もあるようです。
その際も玄関の近くなど、人目に触れる場所を避けるようにしてください。
お屠蘇は飲んでも夜だけに

おせちと同じくお正月の縁起物であるお屠蘇は、喪中には基本的に飲まないほうがよいでしょう。
付き合いなどで飲みたい場合は、厄を払う意味を込めて夜にのみ飲むほうがよいとされています。
日中は縁起物としての意味合いが強いため飲まないようにしましょう。
お年玉は「お小遣い」として

喪中にお年玉を渡すことは、本来は避けるべきとされています。
お年玉は、かつて鏡開きした餅を分け合ったことに由来し、神聖なものとされたためです。
しかし、毎年恒例のお年玉をあげないと、わが子や親戚の子どもたちを悲しませてしまう…と思われる方も多いでしょう。
そのようなときには、華やかなポチ袋や「お年玉」の表書きを避け、「お小遣い」の名目で渡すとよいとされています。
神社への初詣、忌中は避けて

故人が亡くなってから四十九日まで(神道では五十日まで)を「忌中」といいます。
神道では、忌中には「死のけがれ」があるとされます。
この期間は、神社に立ち入るべきではたいため、神社への初詣は控えましょう。
忌が明けた後、悲しみを癒す期間である「喪中」には、神社へ初詣に行っても問題はありません。
なお、死を「けがれ」とする考えのないお寺への初詣は、忌中・喪中共に問題ないとされています。
喪中のお正月は温かい家族の時間を大切に

大切な方をなくした悲しみを癒す期間である喪中には、お正月も普段とは違った配慮が必要です。
とはいえ年末年始の休暇は、家族団らんの時間を過ごす大切な機会でもあります。
お互いの近況を語り合うのはもちろん、故人の思い出話に花を咲かせるのも、喪中のお正月にふさわしい過ごし方といえるでしょう。
いつも通りの「おせち料理」は控えるべきとされていますが、「ふせち料理」を購入したり、食材を選んで手作りしたりすれば食べることも可能です。
また、準備の手間が少ない「お取り寄せグルメ」を頼んで、家族全員でゆっくり過ごしてもよいでしょう。
大切な方を思いやりながら、ご家族で温かなお正月をお過ごしください。